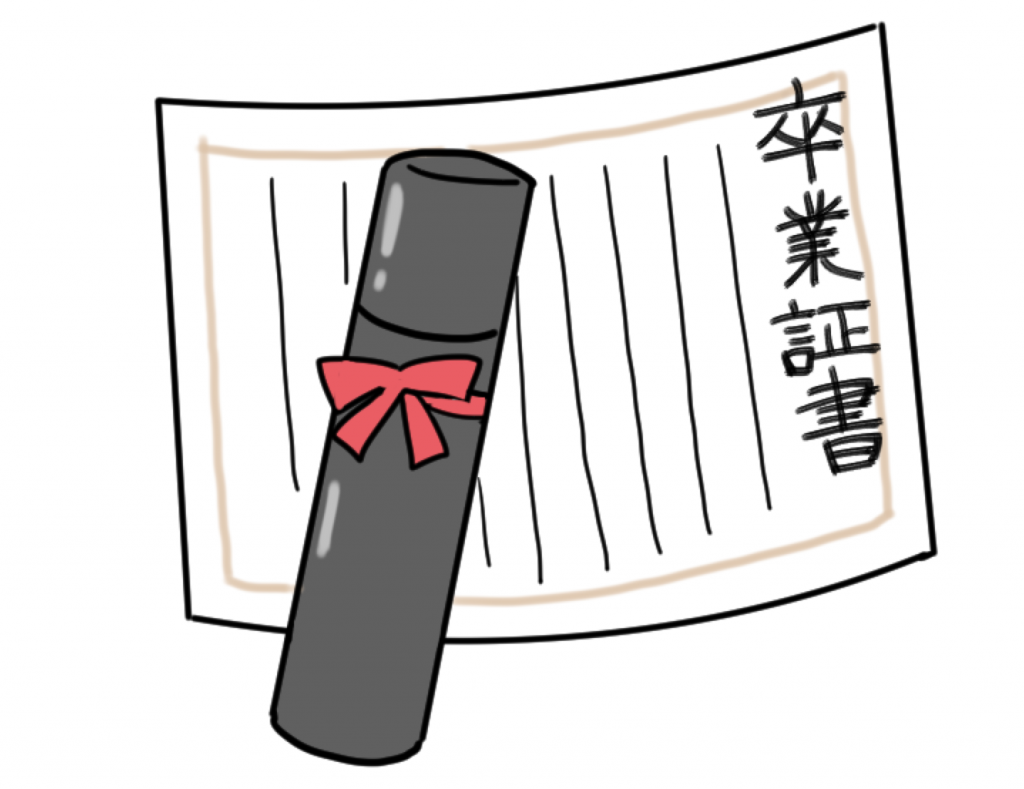11月16日
「こんにちは、坂野研一です。よろしくお願いします。」
「おいでいただきありがとうございます。武志のじじいです。こちらこそよろしくお願いします。先生。」
そう言うと、じいちゃんは深々と頭を下げた。
「どうしたのじいちゃん。ずいぶん礼儀正しいね。それに、先生って何?」
「囲碁ができる少年て聞いたから、せっかくだし教えてもらおうと思ってね。ささ、先生、どうぞこちらへ。」
「はあ、、、」
面食らってる研一の顔をはじめて見た。
「さあ先生、こちらでございます。ささ、上座へどうぞ。」
「じいちゃんの家に、こんな立派な碁盤あったんだ。」
「借りてきた。」
まったく何考えてるんだろう。でも、じいちゃんならこのくらいの反応は想定内。
「あのー、そろそろ『先生』っての、やめてもらえますか?何だか居心地悪くて。」
「ははっ、そうだよね。ごめんごめん、それじゃあ研一くん、改めて一局お願いできますか?」
「よろこんで。」
「研一くんの実力はどれくらい?」
「一応アマチュアの2級クラスってことになってます。」
「うわー、ぜんぜん敵わないや。3目置いて丁度かな。いや、それでも負けそう。」
「じいちゃんて、囲碁できたんだ。」
「おう!じいちゃんは大抵のものはできるんだ。すごいべ。でも、残念なことにどれも強くない。『知ってる』に毛が生えた程度。」
「それじゃ、お願いします。」
そう言うと研一は、唯一黒石のない隅に白い石を打ち込んだ。
「本蛤の石だよ。どお?」
「はい、いつも行ってる囲碁クラブでは、こんないい石使ってません。すごく高いんですよね。」
「本当の本物だと、何百万らしいよ。これはメキシコ産。それでも数万円だって。」
「うわー、緊張する。」
「相手を緊張させるのも、こっちの作戦です。」
そう言うと、じいちゃんは黒石をそっと置いた。
囲碁なんてよく知らないし、見てるだけってつまんない。この勝負、どれくらいで終わるのだろう。
「じいちゃん、コーヒー出すね。」
「おう、ありがとう。」
「西野さん、とお呼びしていいですか?」
「ホントは『西野くん』て呼んでほしいけど、それでいいよ。」
「西野さんは時々囲碁を打ってるのですか?」
「いや、たまーにテレビで囲碁の試合見るくらい。高校の時ね、週一時間だけ『クラブ』っていう時間があったんだ。部活じゃないよ。『クラブ』。そこでね、なんとなく『囲碁クラブ』に入ったの。囲碁の得意な先生が担当で、クラブ員は10人いなかったような気がするなあ。そこで、週一回だけ碁を打ったのが最初の対局。で、なぜかその年の『県高校囲碁選手権』という大会に出ることになって、その時だけ本気で練習した。」
「大会、どうだったんですか?」
「実力10級で申請して、同じくらいの人と対戦したけど1勝3敗。」
「でも、じいちゃん1勝したんだ。」
「実力は向こうが絶対上だった。油断してたみたいで、こっちがでかい石取ろうとしてるのに気づかなくて、うまく引っかかったみたい。こっちはラッキーだったけど、相手はそうとう悔しかっただろうと思う。ところで、研一君はどうして囲碁始めたの?」
「僕は、じいちゃんが囲碁好きで、囲碁クラブにも、最初はじいちゃんに連れられて行ったんです。幼稚園の時でした。年寄りが多いクラブなので、小さい子供が来るとアイドルみたいに可愛がってもらって、お菓子をもらったりしてるうちに、いつの間にか囲碁をさせられてたって感じです。」
「じゃあ、経験は研一くんの方がずっと長いね。」
「ところで武志。朋ちゃんの授業は進んでる?」
「うん、今月は『違う角度から考える』っていうテーマ。写真の子ども見せられて、物語作れっていう宿題からスタートしたんだ。足立裕介さんは、じいちゃんの授業でやったって話してたよ。」
「うん、思い出した。物語作ると、なんとなく親近感が湧いてきて、いじめなんかなくなると思ってやった。」
「で、いじめ防止に役立ったの?」
「そりゃわからんよ。でも、マイナスにはなってないと思う。朋子も裕介も覚えてていたのなら、まあ役立ったと言えるかなあ。うわっ、研一くん、そこ入ってくる?!」
「そろそろ入らないと地合いで負けそうですからね。」
「囲碁って、なんだか人間を意地悪にするみたいだな。さあ、どうしよう・・・」
「でも西野さん、久々の対局にしてはずいぶん上手ですよ。」
「実は、この碁盤借りた友達のところで、3日間練習したのよ。こっちは40年振りくらいだから勘が鈍くてぜんぜんだめだった。でも、繰り返しやってるとね、『この手、よくわかなんないけど、何かあるに違いない。きっと何か企んでる。』と感じるようにはなったかな。まあ、感じただけで何も対応できずに負けちゃうんだけどね。」
勝負は、研一がじいちゃんを圧倒し、30分足らずで終わってしまった。
「ありがとうございました。3目くらいのハンデで勝とうとした自分が浅はかでございました。」
「いえ、勝負を避けて囲われたら勝てなかったと思います。西野さん、場面場面でしっかり勝負して下さったんで、何とか逆転できました。」
ふーん、そういうものなのか。
囲碁なんてあまり興味ないけど、ルールくらい知っててもいいかも。
「ところで、さっき『囲碁は人間を意地悪にする』って言ったけどね、あれってホントだよね。だって、『相手はきっとこんなことを考えてる。ならばそれをさせないように、ここに石置いちゃうもんね。』って考えて勝負してるわけだからね。」
「そうですよね。囲碁や将棋って、だまし合いみたいなところ、ありますもんね。」
「性格、出ちゃうよね。だから、相手の性格を読み切った方が有利になることも多いね。」
「それあります。いつも対局してる相手だと、『きっとこう考えてる。』って感じることあります。」
「そう考えると、囲碁って『違う角度から考える』っていう朋ちゃんのテーマに近い世界かもしれないね。」
「研一が物語作る天才なのって、囲碁と関係あったってこと?」
「それはわからないけど、研一くんは、たくさんの大人と関わっているから、相手の立場で考える習慣が身についてるのかもしれないね。」
「じゃあ、囲碁仲間に感謝しなくちゃ。こんど囲碁クラブに行ったら、対局前に『佐藤さん、僕を大人にしてくれてありがとうございます。』って言ってみようかな。」
「研一くんも策士だねえ。相手を動揺させる作戦だな。」
「わかりました?」
「それにしても、朋子と裕介は素晴らしいテーマをくれたね。違う視点で考えることって、どんな場面でも必要なすごく大切な事だよね。
人と関わったら、『相手は何を感じてるかな。自分をどう思ってるかな。』
問題に直面したら『他に解決策はないかな。自分の考えだけで決めて大丈夫かな。』
欲しいものがあったら『買う意外に方法はないかな。』
いや、万引きするという意味じゃないよ。借りるとか、実は家にあるもので代用できるとかね。
人は誰だって色眼鏡をかけて世の中を見てる。『自分は冷静に公平に世界を見てる。』って断言できる人なんていないよ。だから、『自分の見てるもの、考えてることが全てではないし、一番正しいとも限らない。』と思ってまちがいないね。この視点は、二人とも大切にしていって欲しいな。」
◇ ◇ ◇
「武志のじいちゃん、おもしろいね。いきなり『先生』には参ったけど。」
「うん、ああいう悪戯みたいなこと好きみたい。」
「でも、なんか楽しそうにしてていいね。」
「確かに、ぶつぶつ文句を言い続けてるじいちゃんじゃなくて、そこは良かったと思う。」
「なあ武志。俺もお前もさあ、70歳になってる瞬間て、きっと来るんだよなあ。それって信じられる?頭じゃわかってるんだ。将来じいさんになるってこと。でも、『今、私は70歳のじいさんである。すでに人生の70年は終わった。残りは10年か20年か、それくらいだ。』って考えてる瞬間が来るって、何だか実感湧かないんだよね。その時の気持ちってどんな感じかなあ。」
「研一、そんなこと考えてたの?」
「うん、西野さんと囲碁打ってた時ね、自分が西野さんで、孫が連れてきた友達と対戦してるとしたら、どんな感じかなあ。若い高校生がうらやましいとかあるのかなあ。それとも、いろいろめんどくさい人生を通り過ぎて、すっきりしてんのかなあ。なんてね。」
「そんな風に考えたこと、ないな。」
「すっきりしてて欲しいなあ。」
そう言うと、研一は黙ってしまった。
二人で歩きながら、僕は70歳の老人が二人並んで歩いていく姿を想像した。寂しさ、うまく体が動かないもどかしさ、近づいてくる死への恐怖、あまり良い感情が浮かばない。きっと研一も同じことを考えているのだろう。さっきの「すっきりしてて欲しいなあ。」という言葉は、『願い』を通り越して『祈り』に近いのかもしれない。
ほんとに70歳になった二人が歩いているかもしれないと思った瞬間、研一という存在が、なんだかとても大切に感じた。