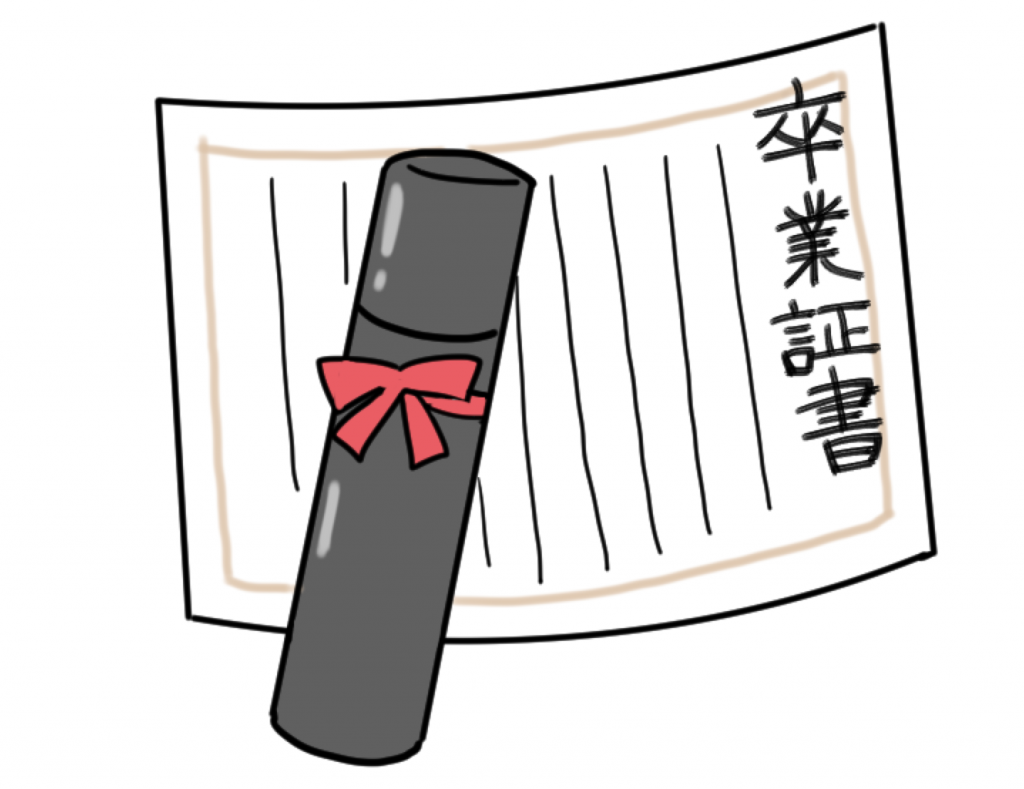11月12日
通学電車の中で、サラリーマンを見ると、いろいろな想像をするようになった。朝起きて、ご飯を食べて、子どもとちょっと話して、そして出かける様子や、会社で仕事をしている姿とか。今までだって、「この人、どんな仕事してるのかな。」とか、「仕事、何時までやるのかな。残業とかあるのかな。」なんて漠然と思ったことはあった。
だけど、今はその人の生活を映像としてイメージしてしまう。
かっこつけると、その人の人生をイメージできるようになった。
もちろん、そのイメージが正しいはずはないけどね。
この電車の中にいる人の全てに人生があって、それぞれ自分の考えとか気持ちで行動していて、あの人から見ると僕は、同じ電車に乗ってるただの「高校生」。
友達という存在も「高校生の間、一緒に行動した同じ年代の人々」だけど、友達から見た僕も同じ。決して特別な存在じゃない。その友達がどれだけ大切かはともかく、僕の人生は友達の人生とは別だ。
父さんや母さんだって自分の人生を生きている。僕はその子どもという存在。将来、僕が結婚して子どもができたとしても、僕は僕の人生を進む。きっと大切になるだろうけど、子どもは子どもの人生を進む。じいちゃんは、母さんの父さんで、僕のじいちゃんだけど、じいちゃんから見れば母さんは子どもで僕は孫。じいちゃんは、母さんや僕のためだけに生きてるわけじゃなく、じいちゃん自身の人生を進む。
そんなの当たり前じゃん。
でも、その当たり前のことを今まできちんと意識したこと、今まであっただろうか。
頭ではわかっているはずなのに、心のどこかで「世界の中心に自分がいる。」「自分を中心に世界が回っている。」「自分の回りの人や物は、自分のために存在する。」と感じていた。小さい頃は確実にそう信じていた。高校生になった今も、大して変わってない。こんなこと口にしたら「あほかお前。」って言われるだろう。「自己チューもたいがいにしろ!」だな。
なんか、寂しくなってる自分がいる。
おーい、武志!お前、もう赤ちゃんじゃないんだぞ。
みんなが自分のために存在するなんて有り得ないじゃないか。
それでも、どこか寂しい。それから、すごいプレッシャー。
自分の人生をどうするかなんて、自分にしかできないのだから。家族や友達だって、自分の人生をどうするかを考えて生きてるんだから。
「わかってる」ということと、「きちんと意識する」ことって、全然違う。
◇ ◇ ◇
「研一、おはよう。」
「おう、武志。どうだ、順調に成長してるか?」
「お前、相変らず直球勝負だな。最近さあ、サラリーマン見て生活をイメージするっていうか、映像化して見るようになった。」
「惜しみない拍手を送ろう!」
「ホントに拍手するなよ。
ところで研一の方は? ていうか、研一はイメージの天才だから成長もないか。」
「天才は、ちょっとしたきっかけで大きく変化できるもんだ。だから天才なんだ。」
「じゃあ、その天才の変化はなに?」
「あのな、この間囲碁クラブに行って、いつも通りじいちゃんとやってたわけ。碁を打ちながら、相手のじいさんのこれまでの人生をイメージする。特に高校時代だ。何が流行ってて、何に興味を持ってて、部活動は何をしてて、当時の大好物は何だったか、それを予想する。「佐藤さんは、高校時代野球部だった。甲子園を目指してたが、残念なことに県大会の準決勝で負けちゃった。学校では歴史の授業が好きだった。だから時代物の小説をたくさん読んでた。好きな食べ物は焼きそば。実は好きな同級生がいたけど、声をかけられずに卒業したのを後悔してる。」とかね。
それから質問するんだ。「佐藤さんの高校時代って、どんな感じでした?」ってね。すると、若い頃のいろんなエピソードや時代の雰囲気を話してくれるんだ。じいちゃん達の話と自分の予想のギャップを、心の中でびっくりしたり楽しんだりしてる。」
「そんなこと考えながら、囲碁ってできんの?」
「若干集中が途切れるから、実力が出ない時もある。でも、若い頃の話を始めたじいちゃん達の方が気持ちを乱してるみたいで、ポカが増えた気がする。で、対戦成績はあんまり変わってないかな。でも、昔の話聞いて、「うわー、今と違いますね。」とか「イメージ変わりました。」なんてリアクションすると、じいちゃん喜んじゃって、「研一くん、またやろうな。」って言われるし、人助けになってるかも。」
「研一って、ほんと、スゲーな。」
「ありがと。でも、武志の素直さもスゲーって思うよ。」
「なんだそりゃ?」
「自分よりも他人の方がよくわかってる、ってこともあるわけ。」
「褒めたの?」
「褒めたんだよ。ところで、一度お前のじいちゃんに会ってみたい。」
「へーっ。うちのじいちゃん、おもしろいけど変わってるよ。」
「なんかちょっと、興味ある。」
◇ ◇ ◇
「もしもし、じいちゃん。」
「武志か。どうした?電話なんてめずらしいな。」
「あのさあ、16日の午後、あいてる?」
「ちょっとまって・・・大丈夫、あいてるよ。」
「遊びに行ってもいい?友達一人連れて。」
「ほーっ!そりゃすごい。彼女か?」
「じいちゃん何想像してんの。高校の同級生。男。」
「なんだ、恋人じゃないの。でも、もちろん大歓迎。連れておいで。」
「じゃあ、2時くらいに行くね。」
「どんな子?」
「町の囲碁クラブでじいちゃんたちと対戦してる高校生。珍しいでしょ。」
「おもしろそうな子だね。楽しみになった。」
「じゃあ、よろしくね。」
「じいちゃん、OKだって。」
「じゃあ、1時に学校ね。」
◇ ◇ ◇
「ねえ父さん。父さんの高校時代って、何流行ってたの?」
「うーん、何だっけな・・・。父さんが高校生の時、ちょうど昭和から平成に変わったからな。あのときは・・・
ちょっと待てい!そんな時のためにスマホがある。えーと・・・おー、すごい!ベルリンの壁崩壊!テレビで見たけど、あれはすごかった。東ドイツがなくなっちゃったんだからね。それから・・・ドラクエ!そうそう、父さんもけっこうハマった。スーパーファミコンていうゲーム機があったのよ。」
「父さんはどんな高校生だった?」
「今じゃ考えられないけど、サッカーづけの毎日だったな。まだJリーグなんかなかったけど、それなりにサッカーは人気のスポーツだったよ。中学も高校も、大した強豪じゃなかったからあんまり勝てなかったけど、我が青春はサッカーと共にあり、って感じだな。」
「Jリーグ、なかったんだ。」
「父さんが大学生になってから始まった。ヴェルディ川崎と横浜マリノスの試合、実は入場券の申し込みもしたんだけど、抽選はずれてテレビで見たよ。それでも興奮したねえ。それからは日本中がサッカーで盛り上がって、小さな町にもサッカーのスポ少がどんどんできたっけ。もし、父さんにもう少し力があったら、Jリーグで大活躍して、今ごろテレビでサッカー解説者なんかやってたかもね。はっはっは。」
「ふーん、そういう時代だったんだね。」
「そう、父さんにとってはいろんなことが変化した時代。でもね、サッカーのプロになれなかったけど、ぜんぜん後悔してないよ。もしプロになってたら、母さんと出会わなかっただろうからね。ねえ母さん、今の聞いたー?」
最後はいつもこれだ。